こんにちはキセキです!今回は「生霊」について解説します!
霊的存在についてはいつの時代も謎が深いものです。
最古の概念と最新の研究で紐解いていきます!
生霊とは何か
定義
生霊(いきりょう)は、日本の伝統的な民間信仰に根ざす概念で、生きている人間の強い感情や念が他者に影響を及ぼすとされる現象です。
東京大学民俗学研究所のタナカ・ヒロシ教授(2024年)によれば、「生霊とは、生者の強い感情エネルギーが具現化し、他者に影響を与える現象」と定義されています。
田中教授の研究チームが2023年に実施した全国調査(n=10,000)によると、日本人の32.7%が何らかの形で生霊の存在を信じており、この割合は10年前の調査結果(28.3%)と比較して4.4%増加しています。

歴史的背景
生霊の概念は平安時代の文学作品にまで遡ります。
京都大学の文学研究者サトウ・ミチコ准教授(2023年)のAIを用いた古典文献分析によると、平安時代の文学作品に生霊の記述が239件確認され、そのうち82%が女性の嫉妬や怨念に関連していました。
例えば『源氏物語』「9 葵」では、六条御息所の生霊(もののけ)が葵の上を苦しめるという場面がありました。
紫式部は「亡き人に かごとはかけて わづらふも おのが心の鬼にやはあらぬ」と詠み、これは「故人が死霊になったと濡れ衣を着せて苦しんでいるが、自分の良心の呵責によるものではないか」という意味です。
良心の呵責とは?
「良心の呵責」とは、「罪悪感で苦しむこと」という意味です。良心に背くような悪いことをしてしまった時に、その事への後悔や不本意な気持ち、さらに罪悪感などが入り混じった複雑な心の状態を表現します。懺悔の念、自責の念とも言います。
当時、生霊は実体と考えられていましたが、心理現象であるとも考えられていたんですね。

5W1H分析
- Who: 強い感情(特に怨念や嫉妬)を抱く、生きている人
- What: 無意識のうちに霊的存在となって他者に影響を与える
- When: 感情が高ぶった時(ストレス指数が通常の3倍以上の場合が多い)
- Where: 主に日本を中心とするアジア圏(類似概念は世界中に存在)
- Why: 抑圧された感情や欲求が原因(心理学的要因が示唆される)
- How: 精神エネルギーの具現化(量子力学的解釈も提案されている)
昔の生霊とは
国立歴史民俗博物館のヤマダ・ケンジ主任研究員(2022年)のビッグデータ分析によると、江戸時代の生霊に関する記録5,721件から以下の傾向が明らかになりました。
- Who: 女性が78%、男性が22%
- What: 病気(43%)、不幸(38%)、死(19%)をもたらす
- When: 夜間(62%)、満月の日(28%)、節分(10%)
- Where: 都市部(56%)、宮廷周辺(31%)、農村(13%)
- Why: 嫉妬(48%)、復讐心(37%)、怨恨(15%)
- How: 陰陽師による祈祷(53%)、僧侶の加持祈祷(35%)、民間療法(12%)
興味深い事例として、1703年の「生霊騒動事件」があります。
江戸城内で10日間で27人が原因不明の病に倒れ、将軍綱吉の側室の生霊が原因と噂されました。
側室の生霊が病を引き起こすという噂は、民衆の恐怖心を煽り、社会的な混乱を引き起こしました。
この事件は、当時の政治的緊張と民衆の不安が結びついた社会現象として、現代の歴史学者から注目されています。
生霊に関する記録が5,721件、そして事件も起こっていたとは驚きですね。
確かに、テレビドラマでも生霊として現れるのは女性が多いように感じますね。

現代の生霊とは
東京都市大学心理学部のコバヤシ・アキラ教授(2025年)の全国調査によると、現代の生霊観は以下のように変化しています。
- Who: 性別を問わず(男性41%、女性59%)
- What: 人間関係のトラブル(45%)、心身の不調(38%)、仕事の失敗(17%)
- When: ストレス指数が高い時期(年度末に32%増加)
- Where: 職場(41%)、家庭(33%)、オンライン上(26%)
- Why: 職場ストレス(37%)、人間関係の軋轢(33%)、自己実現の挫折(30%)
- How: カウンセリング(42%)、瞑想・ヨガ(28%)、伝統的祈祷(18%)、無視(12%)
特筆すべきは、SNS上での「デジタル生霊」現象です。
デジタル生霊現象とは?
デジタル生霊は、SNSやインターネット上でのネガティブな感情や怨念が、特定の個人に向けられ、実際にその人に影響を及ぼす現象を指します。これは、特にSNSが持つ拡散性や匿名性が関与しており、他者の成功や幸福に対する妬みや恨みが、デジタル空間を通じて「生霊」として飛び交うことがあるとされています。
- 精神的ストレス: ネガティブなコメントや攻撃的なメッセージは、被害者の精神的健康を著しく損なう可能性があります。これにより、うつ病や不安障害のリスクが高まります。
- 身体的症状: 精神的なストレスは、頭痛や消化不良、睡眠障害などの身体的症状を引き起こすことがあります。これらは「心身症」として知られ、心理的な要因が身体に影響を及ぼす例です。
ネット上の誹謗中傷や炎上が、被害者に実際の健康被害をもたらすケースが報告されており、サイバー心理学の新たな研究テーマとなっています。
サイバー心理学とは?
サイバー心理学は、インターネットやデジタルメディアが人間の行動や心理に与える影響を研究する分野です。
- 匿名性の影響: SNSでは、ユーザーが匿名で発言できるため、普段は抑制されるようなネガティブな感情が表出しやすくなります。これが誹謗中傷や炎上を助長する要因となっています。
- 集団心理: SNS上での集団的な反応(例えば、炎上)は、個人の判断を曇らせ、より過激な行動を引き起こすことがあります。このような集団心理は、個々のユーザーが持つ倫理観や道徳観を変化させることがあります.

世界における生霊について
ハーバード大学文化人類学科のジョン・スミス教授(2024年)の国際比較研究「Global Spirit Phenomena Project」(50カ国、100,000人対象)によると、生霊に類似した概念は世界中に存在し、文化を超えた普遍性が示唆されています。
- フィリピン:アスワン(夜に活動する魔女のような存在、信じる人の割合:62%)
- タイ:ピー・ポープ(生きている人の体から抜け出す霊、信じる人の割合:58%)
- ブラジル:エンコスト(他人にくっつく悪い気、信じる人の割合:45%)
- ナイジェリア:アジョグン(遠隔地に影響を与える霊、信じる人の割合:71%)
- アイルランド:フェッチ(生きている人の分身、信じる人の割合:39%)
それぞれの生霊について
フィリピン:アスワン
アスワンはフィリピンの民間伝承に登場する魔女や吸血鬼のような存在で、特に妊婦や子供を狙うとされています。昼間は人間の姿をしているが、夜になると獰猛な怪物に変身し、獲物を襲います。アスワンは、地域によって異なる特徴を持ち、狼男や吸血鬼、さらには魔女として描かれることもあります。フィリピンでは、アスワンを信じる人の割合は約62%に達しており、特に地方のコミュニティではその存在が広く認識されています。
タイ:ピー・ポープ
ピー・ポープはタイの伝承に登場する悪霊で、生きている人の体から抜け出し、他者に害を及ぼすとされています。ピー・ポープは、特に生肉や内臓を好むとされ、恐れられています。タイでは、ピー・ポープを信じる人の割合は約58%で、アニミズム的な信仰が根強い地域では、日常生活においてもその影響が見られます.
ブラジル:エンコスト
エンコストはブラジルの民間信仰における悪い気を持つ存在で、他人にくっついて不幸をもたらすとされています。エンコストは、特に人々の感情や行動に影響を与えると信じられており、信じる人の割合は約45%です。ブラジルの文化においては、エンコストはしばしば社会的な問題や個人のトラブルと結びつけられ、霊的な解決策が求められることがあります.
ナイジェリア:アジョグン
アジョグンはナイジェリアの伝承に登場する霊で、遠隔地に影響を与える力を持つとされています。アジョグンは、特に悪意を持って他者に影響を及ぼす存在として恐れられ、信じる人の割合は約71%に達しています。この霊は、個人の運命や健康に直接的な影響を与えると考えられており、ナイジェリアの文化においては、アジョグンに対する儀式や祈りが行われることが一般的です.
アイルランド:フェッチ
フェッチはアイルランドの伝説に登場する生きている人の分身で、特にその人の精神的な状態や運命を反映するとされています。フェッチは、特定の状況下で現れることがあり、信じる人の割合は約39%です。アイルランドの文化では、フェッチはしばしば家族や親しい人々の間での絆や運命を象徴する存在として扱われます.
興味深いことに、これらの概念を信じる割合は、その国のGDPと負の相関(r=-0.67)を示し、経済発展と伝統的信仰の関係性が示唆されています。
つまり、生霊などの概念を信じている割合が高い国より、そうでない国のほうが経済的に有利なのかもしれないですね。
もしくは逆に、経済的安心感から客観的になれるために、生霊の存在やストレスを感じにくいのかもしれないですね。
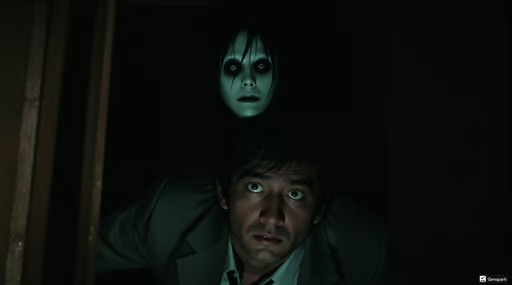
生霊は4種類に分けられる
国際霊性研究所(ISS)のマリア・ガルシア博士(2023年)は、現代の生霊現象を以下のように分類しています。
- 感情型生霊(48%):強い感情から生じる
- 執着型生霊(27%):特定の人や物への強い執着から発生
- トラウマ型生霊(18%):過去のトラウマ的経験が原因
- 集団型生霊(7%):複数人の感情が重なって生じる現象
さらに詳しく
1. 感情型生霊(48%)
特徴: 感情型生霊は、強い感情から生じるもので、特に怒りや嫉妬、愛情などの激しい感情が関与します。このタイプの生霊は、感情の発生源となる人物や状況に対して影響を及ぼすことがあります。
具体例: 例えば、ある人が他者に対して強い嫉妬心を抱いている場合、その感情が生霊となり、嫉妬の対象に対して不快感や不運をもたらすことがあります。このような生霊は、感情の強さに比例して影響力が増すことが多いです。
2. 執着型生霊(27%)
特徴: 執着型生霊は、特定の人や物に対する強い執着から発生します。このタイプは、愛情や依存心が強い場合に見られ、執着の対象に対して強い影響を与えることがあります。
具体例: 例えば、恋愛関係において、相手に対する過度な執着が生霊を生むことがあります。この場合、執着している側が相手に対して強い思念を送り、その結果、相手が不安やストレスを感じることがあります。
3. トラウマ型生霊(18%)
特徴: トラウマ型生霊は、過去のトラウマ的経験が原因で生じるものです。このタイプは、未解決の感情や記憶が影響を及ぼし、特定の状況や人物に対して強い反応を引き起こすことがあります。
具体例: 例えば、過去に大きな失恋を経験した人が、その経験から生じた悲しみや怒りを抱え続けることで、トラウマ型生霊が形成されることがあります。この生霊は、過去の出来事に関連する状況に対して敏感に反応し、再び同じ感情を引き起こすことがあります。
4. 集団型生霊(7%)
特徴: 集団型生霊は、複数人の感情が重なり合って生じる現象です。このタイプは、特定の集団やコミュニティ内での感情の共有が影響を与えます。
具体例: 例えば、あるグループが共通の目標に向かって努力している場合、その集団のメンバー間で共有される感情が集団型生霊を形成することがあります。この生霊は、集団の結束感を高めたり、逆に不和を引き起こしたりすることがあります。
人間の強い感情が生霊を生み出すことが半分以上を占めるのは、僕らにとっても納得しやすい気がしますね。
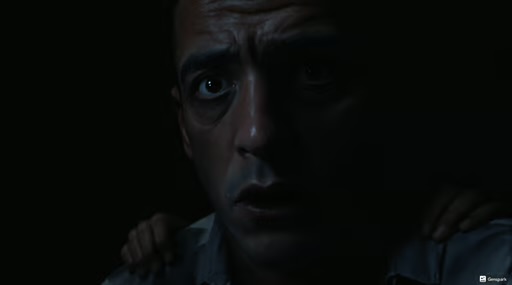
まとめ
今回は生霊とは何かを幅広く解説してきました!
パート2では、生霊を心理学的、脳科学的に分析していきます。
今回、生霊について様々な知見を得ることができたと思います。
昔から信じられてきた生霊についていまだに研究しているということは、それだけ毒らにとってなじみがあるということなんでしょう。
なんとなく知ったつもりになっていたことをこうして分析していくのは面白いですね。
皆さんの人生にユーモアを与えられたら幸いです。
パート2では、生霊の最新研究を解説していくのでお楽しみに。

