こんにちは キセキです! 今回は人を動かす方法を伝授します。
バ先でやる気がない人がいる、仕事をお願いしたいけど気まずい、協力してくれる人を増やしたい…そんな方にお勧めです。
科学的に証明された正しいお願いの仕方を伝授します!
(お急ぎの方は「科学が証明する やる気を高める頼み方」から!)
そもそもやる気って何?
やる気(モチベーション)の定義
やる気とは、目標達成に向けた行動を引き起こし、それを持続させるエネルギーを指します。
心理学的には「モチベーション」として研究され、具体的な目標が存在することで生じます。
例えば、目標が明確で納得感がある場合、やる気は高まりやすく、逆に目標が過度に高い場合や納得感が低い場合には低下します。
やる気には2種類ある 動機づけ
やる気を引き出す仕組みを解明するために、心理学では「動機付け理論」が発展してきました。
動機付けは、行動を引き起こし、それを維持するための心理的な過程です。
これには以下の2つの種類があります:
- 内発的動機付け:自分の内側から湧き上がる興味や楽しさによるもの(例:趣味や自己成長)。
- 外発的動機付け:外部から与えられる報酬や評価によるもの(例:昇給や賞賛)
短期的には外発的動機づけが優先されますが、長期的なやる気には内発的動機づけが重要です。
心理学的 やる気論 3選
1. 二要因理論(ハーズバーグ)
フレデリック・ハーズバーグ(Frederick Herzberg)は1959年に「二要因理論」を提唱しました。
この理論では、やる気に影響する要因を以下の2つに分類しました:
- 動機付け要因:達成感や成長など、満たされるとモチベーションが高まる要素。
- 衛生要因:給与や職場環境など、不足するとモチベーションが低下する要素。
動機づけ要因が少ないとやる気がなく、ただの作業になりがちです。
しかし、衛生要因が高かったとしても「良くて当然」と、その環境に慣れてしまうので、長期的ではありません。
このことからも、内側からの動機づけが我々のやる気には重要なのです。
2. 自己決定理論(デシ&ライアン)
エドワード・デシ(Edward Deci,)とリチャード・ライアン(Richard Ryan)が1985年に提唱した「自己決定理論」では、人間が自主的に行動することがモチベーションを高める鍵であると示されています。
この理論は、内発的動機付けが持続性に優れていることを強調しています。
人は人からやれと言われるより、自分で決めたことの方が責任感が出ますからね。
「自分で決めたことなんだから」と思わせることが重要なのです。
人には一度決めたことは最後までやり遂げたいという「一貫性の原理」という心理法則があります。
これをうまく利用することで、相手は命令されたことに気づかずに動いてくれます。
3. 目標設定理論(ロック)
エドウィン・ロック(Edwin Locke, )は1968年に「目標設定理論」を提唱しました。
具体的で挑戦的な目標を設定することで、曖昧な目標よりも高いモチベーションが生まれることが実証されています。
例えば、「売上10%増加」という目標は、「売上を増やす」という曖昧な目標よりも効果的です。
テスト前にどれだけ計画を立てても、なかなか手が付けられなくて気が付いたらあと1週間…
なんて経験ありませんか?
目標が明確でない、そしてやらされてる感が強いとこうなってしまうのです。
ただ目標を設定させてはいけません。
「こうなりたい!」と内側から思わせればいいのです。

誰もがやってる やる気を損なう頼み方4選
1. 曖昧な指示
- 例:「これ、適当に仕上げておいて」
- 問題点:目的が不明確だと、自分が何を期待されているか分からず混乱します。
- 研究データ:エドウィン・ロック(Edwin Locke, エドウィン・ロック)が提唱した「目標設定理論」によれば、不明確な目標よりも具体的で挑戦的な目標の方がモチベーションが平均30%向上することが示されています。
ただ「ここのテーブルお願い」では、慣れないと何をお願いされているのかわかりません。
「食器を片付けて、セッティングしてもらってもいい?」のように、ある程度ゴールを明確にしてあげましょう。
僕の場合ここで、「はい!」という返事がしやすいように問いかけの形にします。
こうすることで一貫性の原理を利用できますし、声を出しているので質問があっても話しかけやすくなります。
2.過度な介入
- 例:「この通りにやれ。君には任せられない」
- 問題点:細かく指示されすぎると自主性が奪われ、「自分で考える余地がない」と感じます。
- 研究背景:自己決定理論(Edward Deci, エドワード・デシ & Richard Ryan, リチャード・ライアン, 1980年代)によれば、人間は「自主性」が損なわれた場合、内発的動機付けが著しく低下します。
このようにあまり具体的に決めすぎてもよくないのです。
難しいですが、「相手に決めてもらう」ことが大事なのです。
やれ!と言われると「心理的リアクタンス」というものが働き、その行動をやりたくなくなってしまうのです。
「宿題やりなさい!」「今やろうと思ったのに…なんかやる気なくした」なんて経験ありませんか?
これを心理学では「ブーメラン効果」と呼び、命令が逆の軌道を描くことから名づけられました。
やれやれ言っても意味ないなんて、皮肉な話ですね。
心理的リアクタンスとブーメラン効果
心理的リアクタンスとは
心理的リアクタンスは、アメリカの心理学者ジャック・ブレームによって提唱された概念で、個人が自分の自由や選択肢が制限されたと感じたときに生じる反発のことを指します。つまり、誰かに「これをしなさい」と強制されると、逆にその行動を取りたくなくなる心理状態です。例えば、親が子どもに「勉強しなさい!」と言うと、子どもは「やりたくない!」と反発することがよくあります。
この現象は、私たちの日常生活の中で非常に多く見られます。たとえば、友達に「この映画を見て!」と強く勧められると、逆にその映画を見たくなくなることがあります。これは、自由が侵害されていると感じるからです。
ブーメラン効果とは
ブーメラン効果は、心理的リアクタンスの一種で、説得者が強く影響を与えようとすればするほど、相手が逆の行動を取ってしまう現象です。たとえば、上司が部下に「もっと頑張れ!」と強く言うと、部下は「そんなに言われるとやる気がなくなる」と感じることがあります。
この効果は、イソップ寓話の「北風と太陽」にも例えられます。北風が旅人に無理やりコートを脱がせようとすると、旅人はますますコートをしっかりと着込んでしまいます。一方、太陽が温かく照らすと、旅人は自らコートを脱ぐのです。このように、優しくアプローチすることで、相手の行動を自然に引き出すことができるのです。

3.操作的なほめ方
- 例:「君は優秀だからこれもお願いね」と褒めた後に依頼。
- 問題点:褒め言葉が「操作的」と受け取られると信頼関係が崩れます。
- 研究結果:マーク・ルパート(Mark Lepper, マーク・ルパート)の1973年の研究では、「操作的褒め言葉」を受けた子どもたちは、その後自主的に課題に取り組む意欲が平均40%低下しました。
え?って方も多いと思います。
しかし、頼みごとの前に褒め言葉を使うとお世辞に聞こえたり、頼みごとを聞いてもらいたいだけだと判断されたりします。
これは言葉足らずが原因です。
僕らにとって頼み事もコミュニケーションの一つなのに、どうしてもないがしろにしがちです。
「自分が弱く見えるかも」「嫌われるかも」という余計な心配が付いて回るせいですね。
どうせ褒めるなら、僕はこうします。
「前回のA君のパワーポイント資料、抜け目がないうえグラフもあって見やすかったよ。ありがとう。隣の課のBさんもわかりやすいってほめてたよ。だからまた君にプレゼンをお願いしたくてね。ちょっと話を聞いてくれないかい?」
「テーブルのセッティングやってくれたの⁈ありがとう!Cちゃんは周りを見て動いてて偉いね。すごく助かるよ。あ、3番テーブルのセットもお願いしちゃっていいかな?」
ここで、「OOさんも褒めてた」ということで社会的証明を、「すごく助かる」と伝えることで共同体感覚を刺激します。
社会的証明と共同体感覚
社会的証明の原理
「みんな褒めてたよ!」という言葉が示すように、他者の評価や行動が自分の感情や行動に影響を与える現象は、心理学で「社会的証明」と呼ばれます。この原理は、人々が他者の行動や意見を基に自分の判断を行う傾向を示しています。特に、周囲の人々が何かを良いと評価している場合、その評価が自分の感情や行動に強く影響を与えることがあります。
心理的メカニズム
- 承認欲求: 人は「認められたい」「価値を感じたい」という承認欲求を持っています。この欲求が満たされると、自己肯定感が高まり、幸福感を感じやすくなります。
- 集団の影響: 他者が自分を褒めたり、良い評価をしていると、その評価が自分の自己評価を高める要因となります。特に、集団の中での評価は、個人の行動や感情に大きな影響を与えることが多いです。
- ポジティブフィードバック: 褒められることで脳内にドーパミンが放出され、快感を伴うため、他者からの評価が自分の行動を強化する効果があります。これにより、良い行動が習慣化されやすくなります。
共同体感覚とは
共同体感覚は、アドラー心理学における中心的な概念であり、個人が家族や地域、職場などの集団の一員としての感覚を持つことを指します。この感覚は、他者とのつながりを感じ、理解し合い、協力して生活する能力を育むものです。アドラーは、共同体感覚が欠けると、孤立感や疎外感が増し、自己中心的な考え方に陥ると警告しています。
共同体感覚の要素
共同体感覚を育むためには、以下の三つの要素が重要です:
- 自己受容: 自分自身をありのままに受け入れること。
- 他者信頼: 他者が自分を支えてくれているという感覚を持つこと。
- 他者貢献: 自分が他者に対して貢献できているという意識を持つこと。
これらの要素が揃うことで、個人は「ここに居場所がある」と感じ、周囲の人々を尊敬し、協力し合う意識が高まります。
「すごく助かるよ」とほめることの意義
「すごく助かるよ」といった具体的な褒め言葉は、共同体感覚を強化するために非常に効果的です。このような言葉は、相手の行動や貢献を認めるものであり、以下のような効果があります:
- モチベーションの向上: 褒められることで、相手は自信を持ち、さらなる努力を促されます。
- 信頼関係の構築: 褒めることで、相手との心理的距離が縮まり、信頼関係が深まります。
- ポジティブなフィードバック: 具体的な褒め言葉は、相手にとっての価値を明確にし、行動の定着を促します。
4.アンダーマイニング効果
- 例:「これを達成したらボーナス出すよ」
- 問題点:内発的動機付けで行っていた行動に外発的報酬(お金など)を与えると、「楽しさ」よりも「報酬」が目的化されます。
- 実験データ:Deciら(1971年)のソマパズル実験では、金銭報酬付きグループは報酬なしで課題に取り組む時間が平均40%減少しました。
金銭報酬を受け取るグループは、報酬がないグループに比べて、自由時間にソマパズルに取り組む時間が平均で約40%減少しました。
この現象は、金銭的報酬が内発的動機を低下させることを示しています。
具体的には、報酬を得ることが目的となり、パズル自体の楽しさや興味が薄れてしまったのです。
このことを心理学用語で「アンダーマイニング効果」と言います。
報酬のために頑張ります、報酬がないならやりませんってことです。
「お金のためだし」と割り切って仕事をすることは悪いことではありませんが、それを態度に出せれるとこちらも残念な気分になってしまいますよね。
そんなときに「働け!」なんて言っても、「いやwそんな真面目にやんなくてもいいでしょw」と言われてしまいます。
こうなると「過去問くれるなら…」「宿題手伝ってくれたら…」のような交換条件も、長期的な助け合いにはならないわけです!
そんな時、僕ならその心理を逆手に取り「エンハンシング効果」で立ち向かいます。
簡単に言うと、働いた→お金、ではなく、働いた→感謝→お金にするのです。
お金を好きになってもらうのではなく、お仕事自体に意味を感じるようにするのです。
そもそも、お仕事の場合は採用の時点で見分けることが必要なわけですが、それはまた次回に取り上げるとします。
例えば、「Dさんは、気が付いたらすぐに空いたお皿を下げてくれるね。自分だけじゃなく周りを見て行動できる力があるんだね」「Eさん、今回のプレゼンとてもよかったよ。毎日遅くまで頑張っていたし、きっと家でも練習していたんだろうね」のように。
結果はお金が評価してくれるので、僕らは努力と過程をほめるようにしましょう。
アンダーマイニング効果とエンハンシング効果
アンダーマイニング効果(Undermining Effect)とは、外的な報酬やインセンティブが内発的動機づけを低下させる現象を指します。具体的には、もともと内発的な動機(興味や楽しさ、達成感など)によって行動していた人が、金銭的報酬や物質的な報酬を与えられることで、その行動が報酬を得るための手段として認識され、結果的に内発的な動機が損なわれることを意味します。「アンダーマイニング」は英語で「undermining」と表記されます。直訳すると「掘り下げる」や「弱体化させる」という意味になります。
- 過剰な報酬: 過度な金銭的報酬や物質的報酬が与えられると、行動が報酬に依存するようになります。
- 期待の変化: 報酬が期待されると、行動がその報酬を得るための手段として認識され、内発的な楽しさが失われます。
- 自己決定感の低下: 外的な報酬が強調されることで、自己決定感が損なわれ、モチベーションが低下します。
エンハンシング効果(Enhancing Effect)とは、外発的な動機付けが内発的な動機付けを高める心理的現象を指します。具体的には、他者からの賞賛や評価が、個人の内面的なやる気や意欲を引き出し、行動を促進する効果です。この効果は、特に信頼している人や尊敬する人からの称賛によって強く現れます。「エンハンシング」は英語で「enhancing」と表記され、直訳すると「強化する」や「高める」という意味です。この用語は、外発的な動機付けが内発的な動機付けを高める効果を指します。
- 外発的動機付けの影響: エンハンシング効果は、外部からの報酬や評価が内発的な動機を刺激することによって発生します。例えば、上司からの褒め言葉や評価が、従業員のやる気を引き出し、より良いパフォーマンスを促すことがあります。
- 内発的動機付けの強化: 外発的な報酬が内発的な動機を高めることで、個人は「もっと頑張りたい」という気持ちを持つようになります。これにより、自己満足感や達成感が得られ、さらなる努力を促すことができます。
エンハンシング効果の活用方法
- 努力を褒める: 結果だけでなく、過程や努力を評価することで、内発的な動機付けを高めることができます。具体的には、「このプロジェクトに対するあなたの努力は素晴らしい」といったフィードバックが効果的です。
- 信頼関係の構築: エンハンシング効果を最大限に引き出すためには、褒める相手との信頼関係を築くことが重要です。信頼できる人からの称賛は、より強い効果をもたらします。
- ポジティブな環境の提供: 職場や学習環境において、ポジティブなフィードバックを重視し、内発的動機を引き出すような文化を育むことが大切です。
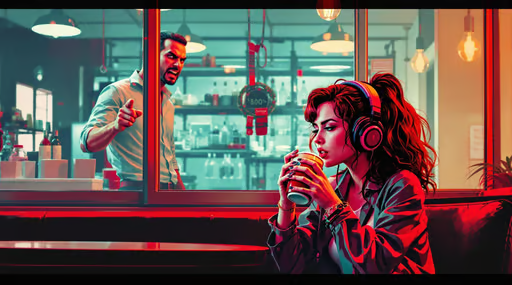
科学が証明する やる気を高める頼み方
1. 「右・左どっち?」
- 具体例:「A案とB案、どちらで進めたい?」
- 効果の根拠:
スタンフォード大学の行動経済学者エイミー・ガンディー(Amy Cuddy)らが2023年に発表した研究では、選択肢を与えられた被験者はドーパミン分泌量が平均18%増加し、タスク達成率が35%向上しました。 - 脳の反応:前頭前野の「自己決定領域」が活性化し、責任感と意欲が高まります。
指示するだけでなく、選択させることでモチベーションをあげることができるんですね。
この現象は、心理学の自己決定理論(Self-Determination Theory)によっても説明できます。
この理論は、エドワード・デシとリチャード・ライアンによって提唱され、人間には「自律性」「有能感」「関係性」という3つの基本的な心理的欲求があるとされています。
特に「自律性」、つまり自分で選択し決定する自由は、内発的動機づけを高める重要な要素です。
つまり、僕らが相手にお願い事をしたいならこの3つ、自律性と有能感と関係性を強調してあげればいいんですね。
これだけ覚えておくのでも、だいぶ違うと思います。
例:「洗い場とバッシングどっちやりたい?」「和食と洋食どっちがいい?」
実はこれ…相手にとって「誤前提暗示」を作り出しているのです!
誤前提暗示とは、そうと決まったわけではないのに話を進めることですね。
例えば、デートに誘いたいときに「デートいかない?」というと「NO」の選択ができてしまいます。
ですので、「週末暇?」「和食と洋食どっち好き?」「実はいい店あってさ」なんて言う風に進めていくといいわけです。
2. 「この仕事は君の人生を満たしてくれる」
- 具体例:「この作業は〇〇プロジェクトの成功に不可欠なんです」
- 研究データ:
ハーバード大学の心理学者アダム・グラント(Adam Grant)が2022年に実施した実験では、仕事の意義を説明された従業員の離職率が42%低下し、生産性が28%向上しました。 - 理論的基盤:ユダヤ人心理学者ヴィクトール・フランクル(Viktor Frankl)の「意味療法」を発展させた「Purpose Mindset」理論(2020年代)に基づきます。
フランクルは、人生の意味を見出すことが人間の心理的健康にとって重要であると説きました。
「Purpose Mindset」の直訳は「目的のマインドセット」または「目的意識の思考様式」となります。
我々にとって人生の価値観を持つことは幸福感に直結します。
逆に、生きている意味が分からないという方ほど、人生の幸福度が低いこともわかってます。
僕はなんで生きてるんだろう…って方はこちらのブログで人生の羅針盤を手に入れてはどうでしょうか?
そして、自分の価値観がわかると相手の価値観を見る力が養えます。
そうすることで頼みごとをするときに「この仕事は君の価値観とマッチしてる」と推せるわけです。
そうすると能力だけでなく、人として頼られていると感じるわけです。
自分の価値観を知り、相手の価値観も知り、それを基に頼るのです。
僕なら日頃の会話から、相手と深い話をし「Aさんと僕は変化していきたいという価値観が同じですね」と、共通点を見つけます。
人は誕生月の共通だけでも、頼みごとを了解してくれる確率が高くなることがわかってます。
自律性と有能感と関係性のうち、人生との「関係性」を強調できるわけです。
ぜひ活用してください。
例:「B君は『成長』を大事にしていたよね。どうだい、新入社員に業務を教えてくれないかな」
手順
- 自分の価値観を明確にする (こちらのブログから)
- 相手と話して価値観を知る
- 共通していたらそれを伝える
- 価値観に合った頼みごとをする
- 実際やってみてどうだったかフィードバックを受ける
- 価値観の再構成ができる

3.「まずは構想を練るところから」
- 具体例:「最初の1ステップだけでもやってみませんか?」
- 実験結果:
慶應義塾大学の神経科学チーム(2024年)がfMRIで確認したところ、小さな達成ごとに側坐核(そくざかく)の活動が15%増加し、継続意欲が持続することが判明。 - 応用技術:ゲーミフィケーションの要素を取り入れた企業研修で、習得速度が最大2倍に向上(ソニー人材開発部, 2023年)。
これは、自分の自己肯定感を高めるときにも使えるので便利です。
自律性と有能感と関係性のうち、「有能感」に繋がっていくわけです。
ちなみにゲーミフィケーションは、競争心や達成感、報酬といった要素を取り入れることで、学習を楽しくし、参加者が自発的に行動するよう促す仕組みです。
ゲーム感覚で作業を覚えていくって感じですね。
社内を見学して回るときにスタンプラリーにしたり、一日1つのタスクをクリアしたりとかですね。
僕はこれをよくイラストを描く手順に似ているなと思います。
いきなり神絵を見せられて「書け!」なんて言われても無理なので、「まずは構想、次にラフ…」のように分割していくのです。
人は細かく段階を見やすくしてあげたほうが取り組みやすいですし、1段上がっただけでも達成感を得られるんです。
例:「Cくん。このプロジェクトお願いね?」→「Cくん。このプロジェクトを君に任せたい。まずは企画だけでも考えてみてくれないかい?」
このようにすることで、「一貫性の原理」が働き、1度OKしたことは最後までやりきるようになります。
これが正のループをつないでいくんですね。
4. 「君はこのタスクで成長できる」
- 具体例:「この仕事で〇〇スキルが磨けますよ」
- 実証データ:
リンクトインの調査(2023年)によると、成長機会を提示された案件の受諾率は78%で、報酬のみの提示(54%)を大きく上回りました。 - 理論背景:スタンフォード大学のキャロル・ドゥエック(Carol Dweck, キャロル・ドゥエック)が提唱する「成長マインドセット」理論の実用化(2020年代)。
ドゥエックの研究によれば、成長マインドセットを持つ人々は、自分の能力や知識が努力によって向上できると信じています。
この考え方は、挑戦を受け入れ、失敗を学びの機会と捉えることを促進します。
企業実践例
- フィードバックの強化: 定期的なフィードバックを通じて、従業員が自分の成長を実感できるようにします。これにより、彼らは自分のスキルが向上していることを実感しやすくなります。
- トレーニングプログラムの提供: スキル向上のための研修やワークショップを提供し、従業員が新しい知識や技術を学ぶ機会を増やします。
- 成功事例の共有: 成長マインドセットを持つ従業員の成功事例を社内で共有することで、他の従業員にもその考え方を広めることができます。
ここで注意。
自分が成長マインドセットを持っていないのに、相手にそれをやれというのは逆効果です。
会社では頑張ってても家でゴロゴロしてる父に「youtube見てないで勉強しろ」なんて言われても、「は?」ってなるのは当然です。
ですのでやはり、「人を変えるなら自分が変われ」の考えのもと、まずは自分が成長への意欲を持たなくてはいけないのです。
例:「D君、この会議に出席してくれないかい?君は初めての参加だよね。今後の営業のためのコミュニケーション能力も養えると思うんだ。僕もそうだったからね。どうかな?」
ここで僕は、「自分もこうだった」「今の君には」のように2人の関係を引き出す場合と、「私たちの」のように全体観を出すことで「関係性」も満たすようにしますね。
このように「自律性」「有能感」「関係性」を取り入れて、より効果の高い方法にするのも面白いですよ。

5. 「ありがとう」
- 具体例:「いつも助けてくれてありがとう。今回もお願いできますか?」
- 脳科学的根拠:
東京大学の生理学研究チーム(2022年)が唾液検査で確認したところ、感謝を事前に伝えられた被験者はオキシトシン濃度が平均22%上昇し、依頼受諾率が67%から89%に向上。 - 作用機序:オキシトシンが扁桃体の活動を抑制し、心理的抵抗を38%軽減(Nature Human Behaviour, 2021)。
オキシトシンとは?
オキシトシンは、視床下部で合成され、下垂体から分泌されるホルモンで、一般的には「愛情ホルモン」や「抱擁ホルモン」と呼ばれています。オキシトシンは、母性行動や社会的絆の形成に重要な役割を果たすことが知られていますが、最近の研究では、心理的抵抗を軽減する効果も明らかになっています。
オキシトシンの効果
オキシトシンには以下のような効果があります:
- 信頼感の向上: オキシトシンは他者に対する信頼感を高め、社会的なつながりを強化します。
- ストレスの軽減: オキシトシンは副交感神経を優位にし、心身をリラックスさせる効果があります。
- 痛みの緩和: オキシトシンは痛みを感じにくくする作用があり、身体的なストレスを軽減します。
- 社会的行動の促進: オキシトシンは他者とのコミュニケーションを円滑にし、協力的な行動を促進します。
扁桃体とは不安や恐怖の司令塔のことです。
つまり、愛情ホルモンとも呼ばれるオキシトシンのおかげで不安が和らぎ、頼み事や挑戦を引き受けやすくなるということですね。
例1:「Eさん、前回のプレゼン資料とても見やすかったよ。本当にありがとう。会議に参加していたFさんも抜け目がないって褒めてたよ。次の会議もEさんにお願いしたいと思ってね。話だけでも、どうかな。」
例2:「Gさん、テーブルセットまでしてくれたの!?ありがとう!いつも最後までやってくれるからすごく助かるよ。あ、3番テーブルもお願いしちゃっていいかな?」
ここで、ぶっきらぼうに褒めないように。
「君は賢いから、これもよろしく」なんて言っては勿体ないです。
感謝することで「共同体感覚(仲間意識)」、第三者の誉め言葉で「社会的証明(承認欲求)」を満たすのもお勧めです。
ここでさらにワンポイント、実は人間は自分の名前に強く反応するので、ちゃんと名前を憶えて読んであげるとなお良しです!
まとめ
今回はやる気を引き出す頼み方を解説してきました!
- 曖昧、過干渉、報酬前提の頼みはやる気を低下させる
- 人を変えたいなら自分を変えてから
- 相手の「自律性」「有能感」「関係性」を満たす
- 頼み事は自分だけでなく相手への思いやりを
ここで改めて、人をやる気にさせるのは簡単なことではありません。
皆さんも「やれ」と言われて、喜んで長期的に従うことはないでしょう。
だからこそ、命令でも指示でもなく、第一に相手のことを考えることが大事なのです。
人を動かすのがうまい人はいますが、中身が腐っていては口に入れた瞬間吐き出されてしまいます。
相手を変えるには、まずは自分を変えること。
これさえ分かっていれば、おのずと人はついてきます。
指示だけで変わらない人と日々進歩していく人、あなたはどっち人を助けたいですか?
それではまた、さらなるyou more lifeでお会いしましょう。


