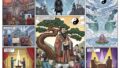こんにちは キセキです! 今回は初配信で使用したブログの完全版を配布します。
聞き取りずらかったところも多々あると思いますので、文字で保存しておきます。
さてさて、人はなんで不安になるんでしょうか?
なぜ人は不安になるのか
脳みその防衛本能
結論:「脳が僕らを生き残らせるため」です。
脳は僕らに危険が近づいているかもしれないと感じると、不安を使って危険に対応しようとします。
脳が不安を感じることは、昔から命が危険になるとされてきたことです。
つまり、僕らの脳は狩りをしていた狩猟時代のまま進化しているのです。
皆さんはどんな時に不安になりますか?
例えば、夜道を一人で歩いているとき。
なんとなく周囲を見回したり、早歩きになった経験はないですか?
これは脳が「敵が隠れてるかも」「今虎が出てきたら勝てないな」と狩猟時代と変わらない危険があると思って不安感を与えてくれてるわけですね。
闘争か逃走か
不安になると心臓がどきどきして息がしづらくなりますよね。
あの嫌な感じは脳と体が「闘争か逃走か」モードになった状態です。
脳は僕らを危険から守らないといけないので、すぐに対応できるように準備してくれます。
心拍数を上げることで、すぐ戦える(闘争)+すぐ逃げれる(逃走)状態になるわけです。
例えばスピーチやプレゼンのとき。
心臓がバクバクして今すぐにでもその場から逃げ出したいことがありますよね。
それは脳が危険を感じた正常な反応なわけです。
狩猟時代にプレゼンはないだろ!って思った方はその通り。
プレゼンはなくても、みんなの前で下手なことすると仲間から嫌われて孤立してしまう危険があったのです。
狩猟時代にとって孤立は命にかかわりますから、脳はみんなに自分をアピールするとき、失敗して嫌われないか不安になるのです。

脳の火災報知器
不安の出どころは扁桃体
現代を生きる我々にとって狩猟時代の不安を持ち出されても困るわけですが、その不安の出どころは「扁桃体」です。
扁桃体は脳の側頭葉にあり、危険を感じたら警報を鳴らすのです。
脳の火災報知機と呼ばれる所以は、ちょっとの不安でピーピー警報が反応するからです。
ちょっと火が上がっただけで警報が鳴り、すぐにレスキュー隊に連絡がいきます。
過保護で優しいお母さん
うっとうしく感じる不安ですが、ないと大変なんです。
例えば寝ているときに火が上がって、火災報知器の警報が鳴らなかったらどうでしょう。
命が危険な状態になるわけです。
そういう場合にいち早く対応するために、ちょっとでも疑わしい場合はとりあえず警報鳴らしとけ!ってなるわけです。
脳は僕らを守るために少々過保護なところもありますが、拳銃をもって走ってくる人を見て不安にならなかったら大変なわけです。

不安を和らげる2つのテクニック
1.呼吸に集中する
不安になった状態は自律神経の乱れを整えてあげることで改善されます。
自律神経には以下リストに挙げた二つがあります。
- 交感神経→吸う息→闘争か逃走か
- 副交感神経→吐く息→リラックス
これを見ていただくと、吸う息が体を「闘争か逃走かモード」にし、吐く息が「リラックスモード」に近づけてくれるのがわかります。
つまり、吸う息より吐く息を長くすることで不安を軽減し、リラックスした状態になることができるのです。
目安としては吐く息を吸う息の2倍にしてみましょう。
4秒吸ったら8秒吐くを繰り返すことで自律神経が整い、リラックスできます。
呼吸をして怒られることはそうそうないと思いますので、不安を感じたらすぐ試してみてください。
2.言語化する
不安は言葉にすることで軽減されます。
これは前頭葉の働きで、体の内側の情報と外側の情報をつないでくれることで不安を軽減します。
前頭葉の内側は僕たちの感情をつかさどり、外側は体の外の情報を分析して扁桃体にブレーキをかけてくれます。
例えば、テストや初デートの前日の夜不安になったら「あぁ、僕は今、明日の試験が怖くて不安になってるんだな。確かに心配だけど、勉強したし明日の朝また復習しよう」という風に。
こうすることで脳が現状を正しく理解することができて、感情にばかり目が行っていた前頭葉に外の景色を見せることで扁桃体にブレーキがかかります。
僕はこれを応用して、「不安に名前を付ける」ということもしています。
不安に名前を付けることで「これ前にも経験したな」と脳に知らせることができるからです。
まとめ
今回は人が不安になるメカニズムと対処法をお話ししました。
不安は生きていくために脳が使ってくれるお守り機能なので、うまく付き合っていきましょう。
そして、たいてい現代の不安は「闘争か逃走か」のうち「闘争」つまり立ち向かわないといけない場面のほうが多いです。
狩猟時代と違って身近な不安への対応が多いからです。
そんな時はぜひ今回のテクニックを使って、不安とうまく付き合い、試練に立ち向かっていきましょう。
皆さんは今不安と戦って努力していますか?それとも逃げて先延ばしにしていますか?
大切なのは、ただ向き合い、受け止めることなのです。